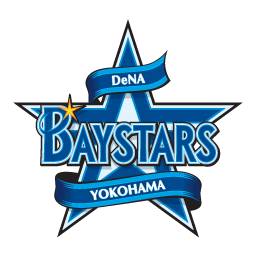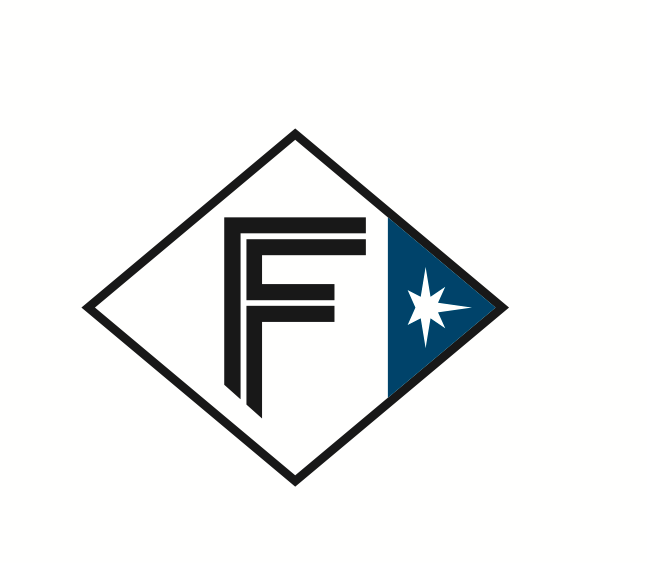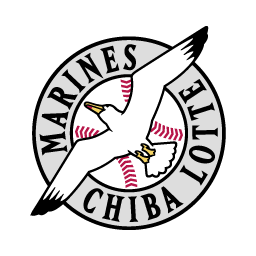海外組がベテラン2選手のみ 海外経験のある選手増加を
2019年女子サッカーワールドカップフランス大会で、決勝トーナメント1回戦敗退と、期待通りの結果を残すことが出来なかったなでしこジャパン。それを尻目に、欧州やアメリカでは、女子サッカーの勢いが急伸している。
日本が再び世界一を奪還するためには、どうすればよいのだろうか。重要なことは、代表クラスの選手の海外移籍と国内リーグの充実化だ。
2011年ドイツ大会で女子日本代表がW杯に初優勝した当時、日本代表メンバーに海外組は4人いた。2015年カナダW杯当時は6人の海外組がいた。一方、2019年フランス大会の日本代表で、海外組は、オリンピック・リヨンのDF熊谷紗希(28歳)と、シアトル・レインFCのMF宇津木瑠美(30歳)で、ベテランの領域に差しかかっている2選手のみだった。
日本の女子サッカーは世界最高レベルだから、なでしこリーグのレベルももちろん高い。しかし、日本人には日本人特有のプレースタイルやサッカーの試合運びがある。海外では、選手の体格やリーチも日本人とは異なり、サッカーの戦い方も日本とは別物だ。
なでしこリーグでプレーするだけでは、世界に通用する技術や連係が身に付いたとしても、場数を踏むという意味では、経験不足に陥ることは否めない。日本の1000人程度の観客と欧州のように数万人の観客が入ったスタジアムでプレーするのとでは、選手にかかる圧力もまるで違う。
大歓声や時には激しいブーイングを浴び、本場のサッカーファンの厳しい目にさらされながら、日常的にプレーしていれば、大観衆に対して精神的な免疫がつくはずだ。そこで日本代表クラスの選手が、10人以上海外でプレーするのが理想だ。
日本サッカー界全体でより一層、女子の海外移籍を支援するとともに、選手達にはもっと外に目を向けて欲しい。
国内リーグは、提携国と協業し活性化
一方で、有力選手が抜けることで、国内リーグが空洞化してはいけない。そこで、Jリーグの提携国と女子についても協力関係を築きたい。
Jリーグ提携国:
タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシア、マレーシア、カタール
なでしこリーグ1部の観客動員が1試合平均1400人だから、その下部の集客はもっと厳しいことは、想像に難しくない。これらの国々のU23代表チームに、なでしこリーグ2部やチャレンジリーグに参戦してもらうのだ。各国のユース代表チームの育成になるだろうし、国際試合となれば、下部の日本人選手の緊張感も増し、観客動員に好影響が期待できて、ウィンウィンだ。
提携国U23代表チームの1部昇格は出来ない規定にするが、カップ戦では、1部クラブとの対戦も実現する。そして、下部で有望な外国籍選手がいたら、選手単位でのなでしこリーグ1部移籍は可能とする。このようにして、アジアの提携国枠各国の人気選手を1部にも吸い上げて、下部から1部まで、海外での注目度を高めて、大手スポンサー獲得や放映権販売を目指す。
国際化で獲得した資金を日本女子サッカーに投資
なでしこリーグの国際化政策により得た収益を、日本の女子サッカーに投入したい。昨季のなでしこリーグの1試合平均観客動員1400人というのは、男子であればJ3下位かJFL上位と同じくらいだ。興行として考えたら、プロクラブとしてやっていけるかどうか、ギリギリのところだ。
男子のJリーグは、プロ化して観客動員数が大幅に伸びたが、それが女子にも当てはまる保証はない。日本では、高校野球や高校サッカーといった育成世代のアマチュアの試合に非常に多くの観客が足を運ぶ。校長先生の一声で、学校総出で応援に来るといったこともあるが、青春や純粋さといった部分に、ファンは魅力を感じているのだろう。
現在なでしこリーグに、プロ選手はいるが、完全なプロリーグではない。彼女たちは、純粋にサッカーが好きだから、競技に打ち込んでいるのだ。それは、人の心を打つ一つの要素だ。
プロ化で選手の生活が助けられるのは確かだが、仕事とサッカーを両立したいという選手もいるはずだ。プロ化ありきで、議論を進めるべきではない。プロを目指すなら、海外に行くことも出来る。プロ化は、日本女子サッカーの発展のための選択肢の一つにすぎない。
女子は、男子と比較して、身体的に成熟するのが早い。中学世代といった、男子ほど充実していない育成世代に資金を回すのも一つの手かもしれない。