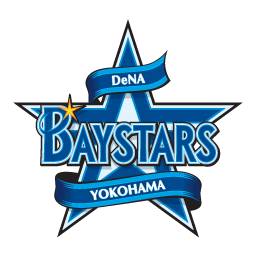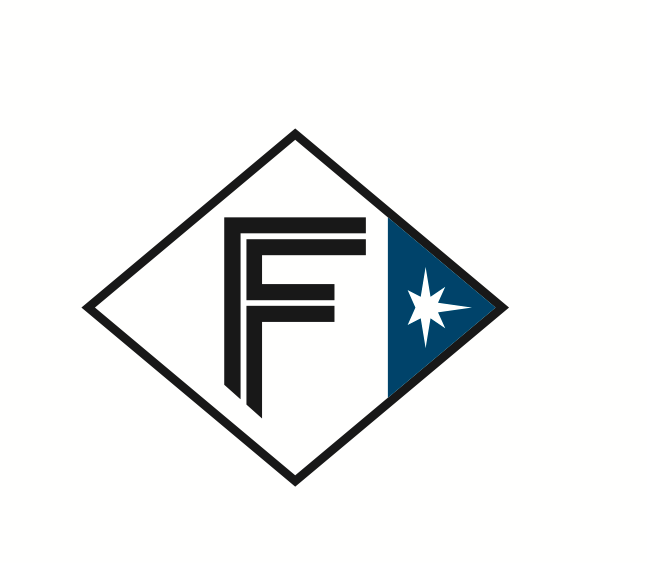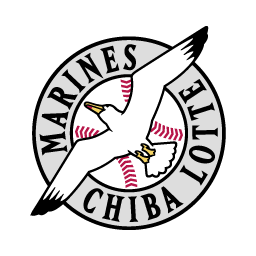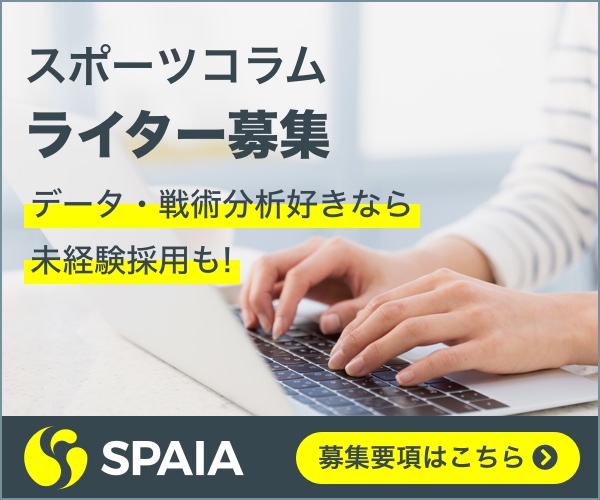休日の部活指導を民間に委ねる「地域移行」
学校単位で教員が原則指導してきた公立中学校の運動部活動が、大きな改革に乗り出した。
休日の部活動指導を地域のスポーツクラブや民間事業者に委ねる「地域移行」を2025年度末までに実現するというのが今回のスポーツ庁による改革の柱だ。
部活改革の背景には少子化による部員減少や、教員の長時間労働の「働き方改革」が求められているため、学校単位での運営が困難になっている現状がある。スポーツ庁の有識者による提言は、山間部や離島を除き、2023~25年度を「改革集中期間」に設定。自治体に具体的な移行プランやスケジュールを定めた推進計画の作成を求めた。
NHKなどの報道によると、スポーツ庁の室伏広治長官は「今こそ改革のタイミング」と明言。地域の指導者確保が重要課題に挙がっており、自治体を財政支援して人材不足を回避していく考えだ。
文化庁の有識者会議も吹奏楽や合唱といった文化系部活動の「地域移行」について議論しており、7月に提言をまとめる。
男子サッカーや女子バレーは30年後半減のピンチ
スポーツ庁が委託した調査で2019年3月に野村総合研究所が公表した「今後30年の部活動人口推計」は、ある意味で衝撃的な結果だった。
それによると、日本中学校体育連盟(中体連)の加盟人数は2018年度の約203万人から2048年度に約148万人へ減少すると予測。競技別に見ると、1校当たりの加盟人数が2048年度に半減以上となる競技は男女とも複数存在する。そのうちピーク時に比べ、1校当たりで男子サッカーは2048年度、女子バスケットボール部は2043年度、女子バレーボールは2045年度に半減するというピンチを迎える。
さらに男子軟式野球、女子ソフトボール、男子ラグビーなどは1チームに形成に必要な人数が下回ると予測されている。スポーツをやりたくても部活がない時代が迫っている。学校単位でチームを組む現在の構造は事実上崩壊しつつあるのが実情だ。
全国で増える複数校による合同チーム
そこで人数不足のチームを救うための苦肉の策として、全国的に増えているのが複数校による「合同チーム」の編成だ。社会の変化とともに、学校の部活動にも柔軟性が求められてきている。
中体連の2021年度統計によると、部活動の「合同チーム」は全47都道府県で結成されており、その数は22競技の1722チーム。2011年度の622チームから3倍近くに増えた。
その中でも部活動の合同チームは2011年度から2021年度までの間に軟式野球が120から693、サッカーも104から330に急増している。かつて圧倒的な人気を誇った野球やサッカーも地方によっては深刻な部員数減少に直面する。
合同チームの基本は「合併型」。野球は9人、サッカーなら11人など、各競技の出場人数に満たない学校同士で組むパターンだ。このほか人数を満たしている学校に交ざる「合流型」や、不足人数を補う「補充型」もあるという。一方で「合流型」は強いチームを意図的につくることへの懸念もあり課題は多い。
指導者確保、課題は山積
運動部活動の「地域移行」で受け皿と期待されているのが全国に約3600設置されている「総合型地域スポーツクラブ」。子どもから高齢者まで地域住民のスポーツ参画を目的に設立され、さまざまな競技で指導資格を持った専門家も在籍する。
一方で受け皿となる地域団体がない地方もあり、自治体には指導者確保も喫緊の課題だ。国は競技経験のある住民や保護者らが資格を取得して指導できるよう研修を充実させる方針で「持続可能な部活」へのシフトには、保護者を含めた住民や行政など地域全体の協力が不可欠となっている。
スポーツ庁によると、民間団体の運営では、指導や保険の費用が従来より1人当たり年間約1万7000円高くなるとの試算がある。会費などの家計負担が学校の部活より重くなるとみられている。
こうした問題を踏まえ、提言では地元企業に資金協力を呼びかけるほか、特に困窮世帯の子どもが参加できるような費用補助が必要とも呼びかけている。
一方、高校における部活改革は、義務教育ではないため各校の実情に応じて検討することとした。
少子化と働き方改革を背景に、公立中の部活動を今後3年でどこまでシフトできるのか。課題は山積している。
【関連記事】
・日本初開催のXゲームズ、若者が熱狂する新世代スポーツの魅力とは
・五輪の近代五種に「SASUKE」導入? 馬術に代わる障害物レースとは
・ブレイクダンスの採点方法やルール、初実施パリ五輪へ福島あゆみが世界一