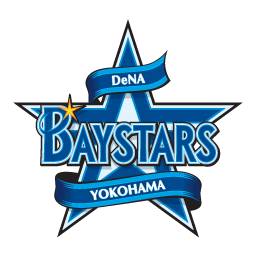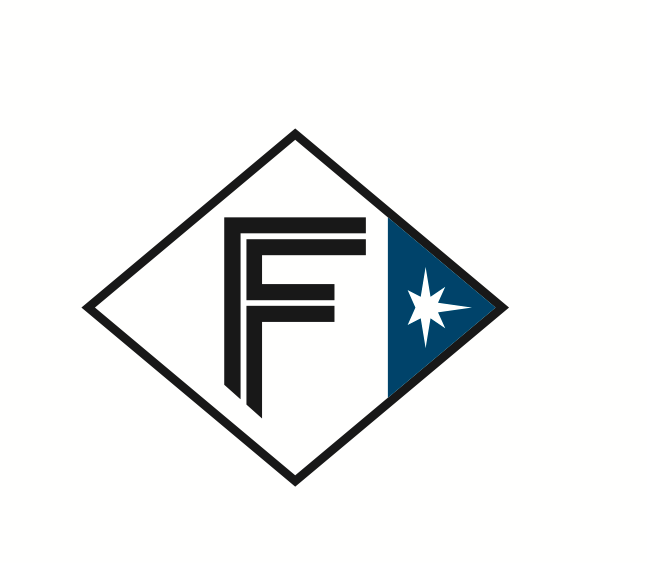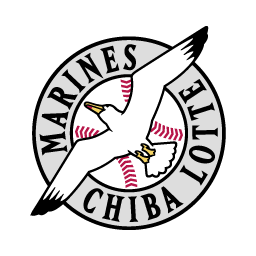フェブラリーSは例年ハイペース傾向、今年はどうか
フェブラリーSはかなりのハイペースになることが多い。東京ダ1600mは芝スタートで序盤からスピードが出るため、前半3Fのペースが速くなること、逃げ、先行馬がそろい4F目(3コーナー)でもあまりペースが緩まないことが影響している。実際、過去10年で前半4Fが47秒を切る速いペースが8回もあり、良馬場でそこまでペースが上がると先行馬が押し切るには、後続馬よりもひとつ上の能力が求められる。
2019年インティが逃げ切り勝ちを決め、2014年にはコパノリッキーが2番手から抜け出して優勝しているが、前記2レースはいずれも逃げ、先行馬が手薄だった年で、前半4Fが48秒0の平均ペースだった。トランセンドが逃げ切り勝ちした2011年も前半4Fを47秒9で通過し、平均ペースの範囲内で収まっている。
今年は何が何でも逃げたい馬が不在、能力値上位の先行馬もアルクトスのみと手薄だ。また、キックバックが苦手で出していく必要性がある昨年のエアアルマスのような馬も不在。ここはテンの速いソダシが逃げ、楽に行けるなら行きたいインティが2番手とスムーズな隊列形成で、そこまでペースが上がらない可能性が高い。重馬場想定で前半4F47秒台前後の通過、1分34秒台の決着になると予想。このペースなら普段それよりも厳しい競馬をしている逃げ、先行馬が楽になるので、今年の穴は「前」と見ている。
能力値1~5位の紹介

【能力値1位 アルクトス】
一昨年、昨年とマイルCS南部杯を連覇。一昨年は1分32秒7の日本レコード決着、砂を入れ替えた昨年は不良馬場ながら時計を要したうえで好時計決着(ハイペース)を大外16番枠から無理なく2列目の外を追走、一昨年を上回る自己最高指数で優勝した。盛岡のダ1600mは東京ダ1600mと同じワンターンコース。2019年の覇者サンライズノヴァが翌年のフェブラリーSで3着に好走しているように、マイルCS南部杯とフェブラリーSは適性が類似しており、この舞台への不安はない。また、昨秋はさきたま杯とマイルCS南部杯を連勝している辺りからも地力強化している。
昨年のこのレースで同馬が2番人気を裏切り9着に敗れたのは、内が極端に浅いダートで内を立ち回った馬が上位を独占した結果だ。そんな中で同馬は好位の外を追走し、4角大外を回るロスが応えたのが一番の要因。
今回は自己最高指数を記録した後の休養明けの一戦となるだけに、ここにピークを持ってくるのは難しと考える。しかし、スタミナが不足する休養明けで、馬場が軽くなるというのはプラスだし、高速決着が予想される中での内枠、好位の内目を立ち回れる点も好材料。前走ほど走れない可能性は高いにせよ、軽視は禁物だ。
【能力値1位 テイエムサウスダン】
古馬の交流重賞では4戦して3勝2着1回、一方、中央重賞では2戦大敗だったことから前走の根岸Sでは6番人気と低評価だった。しかしそれを覆して中央初重賞制覇を達成。ただ、前走はゴールに向かって減速していくかなりのハイペースの消耗戦。11番枠から内の馬の出方を窺いながら、中団馬群の内目に入れ競馬したことでやや展開に恵まれた面がある。
また、ダ1600mでは2戦し結果を出せていないが、1戦目は2歳時の全日本2歳優駿、2戦目は休養明け好走後の疲労残りの一戦となった昨秋の武蔵野Sだ。同レースはラスト2F11秒7-12秒9とラスト1Fで大きく減速しているように激流。内枠だったため好位の内から激流に乗って最後が苦しくなっての9着、敗因が距離とは決めつけられない。それにレースが平均ペースの範囲内で収まる時は、順当に能力上位馬が来ることが多いので、警戒したい。
【能力値3位 レッドルゼル】
昨年の根岸Sで初重賞制覇を達成すると、GⅠ・ドバイゴールデンシャヒーンで2着。そのレースは米国の逃げ馬がレースを引っ張ったことで、先行馬が崩れたもの。中団外を追走したレッドルゼルは展開に恵まれての好走だった。しかし、国際舞台で通用するのは展開の後押しがあっても、地力がなければ不可能。
前走のJBCスプリントでは前半3F37秒0-後半3F36秒0のややスローペースとなった中、12番枠から好位の外目でレースを進めた。そこから3~4角で内に進路を切り替え、4角で位置を押し上げ先頭列に並びかけるようにして直線へ。そのまま突き抜けて3馬身差の完勝だった。
JBCスプリント当日はダートの内が深く、各馬が4角で外目に出して行く中、コーナーロスと引き換えにダートの深い内を選択したものだったが、そこからぶち抜いた内容は本当に強かった。しかし、同馬もアルクトス同様、今回は自己最高指数を記録した後の休養明けの一戦。目標はこの先のドバイだろう。
また、レッドルゼルは本質的にマイルは長く、マイルにも対応させるために、川田騎手が差し馬として育てた馬。昨年のフェブラリーSでも16番枠から好発を切ったものの、ポジションを下げて中団内目で脚をタメることで、4着と善戦した。確かにフェブラリーSは内が圧倒的に有利な状況で、最後の直線では外に出したが、流れは速く、展開には恵まれたことを考えると、悪くはないがワンパンチ足りない。前売りの段階では1番人気だが、臨戦過程と距離を考えると人気ほどの信頼はできない。
【能力値4位 ミューチャリー】
昨秋のJBCクラシックで初G1制覇を達成した地方馬。同レースはダノンファラオやカジノフォンテンが馬場を探りながらのレースでペースが上がらない中、7番枠から1角で外に出し、終始ダートの浅い外から前との差を詰め、3~4角先頭から押し切っての優勝だった。JBCクラシックはさすがに地元金沢を知り尽くした吉原騎手ならではの好騎乗だったが、外から食らいつくオメガパフュームを半馬身振り切り自己最高指数を記録した辺りに地力強化を窺わせた。
前走の東京大賞典はJBCクラシックで自己最高指数を記録した後の疲れ残りの一戦。個人的には消しレベルの評価だったが、4着と善戦した。次走でフェブラリーSを使うことを意識しての早仕掛けだったのかもしれないが、やや速い流れを好位の中目から徐々に位置を上げ3角で2番手、4角ではオメガパフュームを大外に張って先頭で直線に入るなど、攻めすぎの競馬だったが、オメガパフュームと小差だった。
ただ、JBCクラシックを始めダ1800m以上のダ―トグレードでは10戦全て5着以内なのに対して、ダ1600mでは4戦全て6着以下。このことからもダ1600mは距離が短い。もっと厳密に言えば、基礎スピード不足であり、1分34秒台の決着となると、過去2年のように後方に置かれ過ぎて物理的に苦しい競馬になるだろう。過去2年同様に軽視したい。
【能力値5位 ソリストサンダー】
昨年のGⅠ・かしわ記念で2着。同レースはサルサディオーネが前半4F48秒4までペースを引き上げ、3~4角で失速。4角先頭に立ったカジノフォンテンも苦しくなり、ラスト2Fで12秒9、13秒8。ラスト1Fで前が大きく失速したところを、中団外から2着に上がったもの。また、昨年の武蔵野Sでも先行したテイエムサウスダンが9着に敗れたように、速い流れを中団外で我慢させた結果の優勝だった。
同馬はもともとダ1400m以下では序盤で置かれすぎて結果を出せず、距離が延びて追走が楽になったことで結果を出した。前走の根岸Sでも追走に苦労して脚を削がれたような敗戦だった。つまり、ダ1600m~1700mが最適条件であり、内が圧倒的に有利となった昨年のフェブラリーSこそ後方外々から4角大外を回って8着に敗れたが、マイル以上の距離では比較的に安定して走れている。
ただ昨年のフェブラリーSは、13番枠から五分のスタートを切り、中団からじわじわ下がり後方外からの競馬になってしまった。昨秋のマイルCS南部杯のように、時計が掛からないと好位~中団でレースを進められない点がネックだ。時計が掛かれば、相手次第で好位の外まで上がって行けるが、高速ダートとなると位置取りが悪くなりすぎる危険性がある。それでも堅実な末脚を使うので、平均ペースよりも速い流れになると見る今回は警戒が必要だろう。
穴は前に行けるソダシとインティ
【ソダシ】
デビューから5連勝目で桜花賞を制し、昨夏の札幌記念では強豪古馬を相手に強気な競馬で快勝。平均ペースで逃げるトーラスジェミニの外2番手でレースを進め、3角では外から捲ってくるブラストワンピースに抵抗する形で、トーラスジェミニを交わして先頭に立ち、4角から仕掛けてそのまま押し切る横綱競馬を見せつけた。
オークスは休養明けで桜花賞を好走した後の一戦で8着敗退。前に厳しい展開を折り合いを欠きながら先行したこと、3角では進路を失って躓いて下がる不利などが重なり、スムーズな競馬ではなかった。また、秋華賞も休養明けで札幌記念を好走した後の一戦で10着敗退。5F通過が61秒2とそこまで遅くもない中で、2番手のソダシが3~4角の外からエイシンヒテンに競り掛けて一気にペースアップ。これによりラスト3F11秒3-12秒3-12秒9とラスト2Fで大きく減速しているように、前がかなり苦しい展開だった。
オークスも秋華賞も敗因がはっきりしているだけに、個人的には全く気にならない。さらに初ダートの前走チャンピオンズCでも12着に敗れているが、日本の競馬史上、初ダートで国内のGⅠ制覇を達成した馬は1頭もいないだけに、これもまた気にならない(牡馬混合のGⅠでは、2001年のトゥザヴィクトリーのフェブラリーS3着が最高着順、同馬は次走のドバイワールドCでも2着と好走)。
むしろ、前走は坂スタートの中京ダ1800mで初ダートなると出遅れることが多いものだが、ソダシは1番枠からまずまずのスタートを切り、わりと楽にスピードに乗ってハナを取り切っている。序盤でインティに競られてペースを引き上げたこともあり、最後の直線では苦しくなったが、初ダートとしては上々の走りだった。
また、前走ではラスト2Fでジリジリ失速していることから、脚をタメずに逃げるのであれば、距離短縮は加点材料だ。さらに同馬は芝のレースで好発を決めているように、テンでより楽にスピードに乗せられる芝スタートも好ましい。今回はあくまでも挑戦者の立場だが、ダート2戦目というのは、前記のトゥザヴィクトリーのように上昇度が大きいもの。ダートに照準を合わせることで餌やトレーニングもダート仕様になるし、それにともなって走法も変わってくることが多い。そのうえ東京ダ1600mとなると、変化率がかなり高いと見ている。
【インティ】
2019年のこのレースを逃げ切り勝ちした馬。その頃と比べると勢いでは見劣ってしまうが、昨年のかしわ記念3着、秋のマイルCS南部杯、チャンピオンズCは4着と善戦しているように、まだまだGⅠで上位の実力はある。同馬は出遅れて後方からの競馬となった昨年のかしわ記念でも善戦しているように、位置取りよりもいかに自分のリズムで走れるかが重要。
また、同馬は過去3年のフェブラリーSで1着、14着、6着と過去2年は苦戦。対して、チャンピオンズCでは過去3年で3着、3着、4着と安定して走れているように本質は中距離タイプ。1分32秒7の日本レコード決着となった一昨年のマイルCS南部杯では、オーバーペースならぬ、オーバースピードで逃げ勝ち馬アルクトスと2.1秒差(9着)と大敗したように、1分33秒を切るような基礎スピードが求められる競馬では対応できない。
そういう意味では馬場が高速化するのは好ましくないが、控える競馬も板についてきたここは、そこまでペースが速くならないと見ている。また、アルクトスも一昨年のフェブラリーSで内枠から積極的に出してワイルドファラオと逃げ争いをして崩れた苦い経験から、2列目狙いの競馬をする可能性が極めて高い。ここはインティの前からの押し切りを視野に入れてみたい。
※パワーポイント指数(PP指数)とは?
●新馬・未勝利の平均勝ちタイムを基準「0」とし、それより価値が高ければマイナスで表示
例)レッドルゼルの前走指数「-33」は、新馬・未勝利の平均勝ちタイムよりも3.3秒速い
●能力値= (前走指数+前々走指数+近5走の最高指数)÷3
●最高値とはその馬がこれまでに記録した一番高い指数
能力値と最高値ともに1位の馬は鉄板級。能力値上位馬は本命候補、最高値上位馬は穴馬候補
ライタープロフィール
山崎エリカ
類い稀な勝負強さで「負けない女」の異名をとる競馬研究家。独自に開発したPP指数を武器にレース分析し、高配当ゲットを狙う! netkeiba.com等で執筆。好きな馬は、強さと脆さが同居している、メジロパーマーのような逃げ馬。
《関連記事》
・【フェブラリーS】注目ソダシは消し! ハイブリッド式消去法で残ったのはカフェファラオなど最大6頭
・【フェブラリーS】今年も高齢馬が奮戦 五度目の正直サンライズノヴァ
・【フェブラリーS】雨ならキングカメハメハ産駒が主役! 東大HCが東京ダ1600mを徹底解析