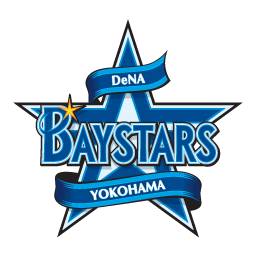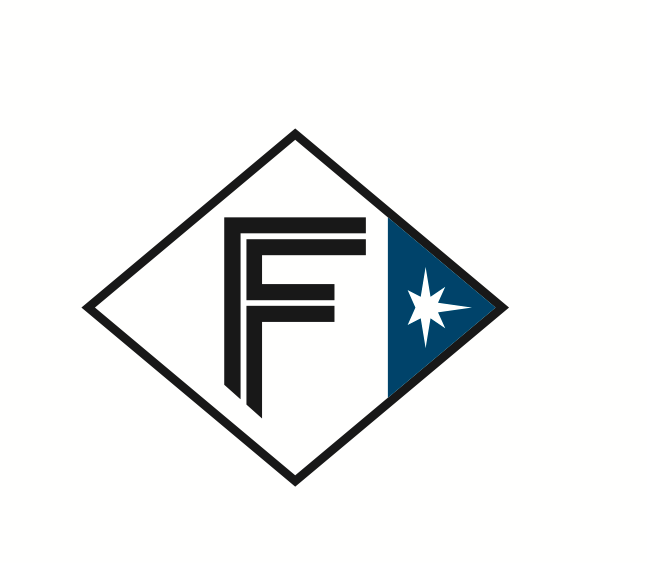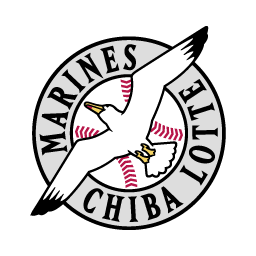流動性と数的有利
これまでのJリーグにも様々な特徴をもったチームはあったが、直近15年ほどの期間、キーワードとなっていたのは「流動性」と「数的有利」ではなかっただろうか。
そのベースにあったのは「日本人らしいサッカー」をしようという考え方。海外の選手に日本人選手はフィジカルでは勝てない。だから、日本人は日本人の特徴が活きるサッカーをしよう。そのためには「流動的に動くことによって局面での数的有利を作る」ことが有効だと考えたのだ。
そういった考え方をベースに高い完成度のチームを作ることに成功したのが、近年の川崎F。
選手が流動的に動き、近い距離でショートパスをつなぐことで局面での数的有利をつくり、突破していく。こういった局面を積み重ねるスタイルで、2017年と2018年に連覇を達成した。
局面から盤面、立ち位置をめぐる争いに
ところが川崎Fの3連覇を阻み優勝を決めた横浜FMは、川崎Fとは異なる考え方で組み立てられた戦術を用いていた。
キーワードは「立ち位置」。ビルドアップもアタッキングサードでの崩しもプレッシングも、全て相手より優位な立ち位置を取ることにより実現しようとする考え方。それぞれの局面ではなく、全体的な盤面を見て自分たちが狙いとする形をつくるために位置取りを徹底するのだ。
この2つの考え方は、同じ攻撃的サッカーであったとしても全く異なる。「局面という小さな場面の集合体が試合」という考え方と、「試合という大きな盤面の中にそれぞれの局面がある」という考え方。スタート地点が全く逆なのである。
そしてこの「立ち位置」「盤面」という考え方は、欧州で積み重ねられいまや主流となった考え方。それをベースにして戦術を組み立てる横浜FMが2019年のJリーグを制したということは、今後のJリーグにとってターニングポイントとなりえる出来事である。
天皇杯決勝でも現れた構図
2019年シーズン最後の試合となった鹿島対神戸の天皇杯決勝も、ハッキリと局面のサッカーと盤面のサッカーが戦う試合となった。
これまで、数多くのタイトルを獲得してきた鹿島は「勝負強い」などと表現されることも多いが、基本的には局面のサッカーである。守備はマンツーマンの要素が強く、流動性や局面での選手の判断を重視する。再現性は低いがそういった中に「サッカーを知っている」と言われるような選手がいて、例え押し込まれても我慢して1チャンスをものにする。そんなサッカーを行ってきた。
一方の神戸は世界屈指のタレントを揃えたタレント軍団ではあるが、調子を上げてきたのは欧州でキャリアを重ねてきたフィンク監督が就任してから。持ち込んだ戦術は「立ち位置」「盤面」を踏まえた欧州ではスタンダードなものだ。
そして、この両者が戦う決勝は神戸が立ち位置を武器にグループとして鹿島の守備を崩していった。得点シーンだけを見るとミスや不運な面もあったが、内容には圧倒的な差があった。
鹿島が後半押し返した様に見えたのは、鹿島がイチかバチかの戦いを挑み、リードしている神戸がそれを落ち着いていなしたからに過ぎない。
増える「立ち位置」「盤面」にこだわるサッカー
ここまでは横浜FMと神戸を例に上げたが、C大阪や大分も同じ様に「立ち位置」「盤面」にこだわるサッカーを披露し、昨季は好成績を残している。
そして2020年シーズン、清水の監督には横浜FMのコーチだったピーター・クラモフスキーが就任。鹿島の監督には、伝統のブラジル人ではあるもののキャリアとしては欧州でコーチの経験を積んできたザーゴが就任した。あの鹿島が選手も含め大きく入れ替える決断をしたことはかなり大きなニュースである。
こうした「局面から盤面」「流動性から立ち位置へ」という流れは、一過性のものなのか。それともこれからのJリーグのキーワードとなり得るのか。2020年シーズンが非常に楽しみである。