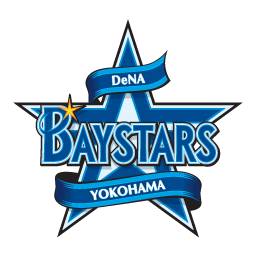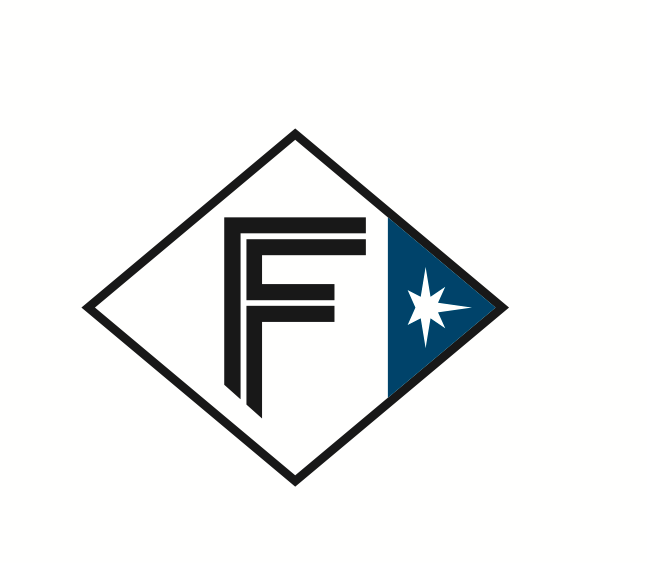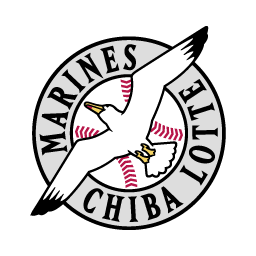ディフェンスの改善と川村の復調で三河が一歩抜け出す
今季のB1残留争いは例年以上に熾烈を極めている。毎年中盤になれば上位と下位の差が開いてくるが、今季は下位が団子状態。中地区2位のシーホース三河を含め、11クラブが勝率5割以下で、これらのクラブが残留プレーオフ争いの候補になってくる。
その中で一歩抜け出しそうな気配があるのが三河だ。当初は大型補強が成功し、中地区の優勝候補に挙げられていたが、なかなかチームが噛み合わず停滞。その原因はディフェンスで、10月末時点での平均失点は84.3だった。その数字を少しずつ改善し、現在は82.8まで減少させた。元々オフェンスが得意な選手が多くハイスコアゲームで勝ち切るクラブだけに大幅な減少こそないが、それでも課題を克服し始めている。
昨年末から1か月間で9連勝を達成し、勝率が上がり切らないクラブが多い中地区で2位に浮上した。ディフェンスの改善に加え、#1川村卓也の復調が大きく、この9連勝の間全て先発出場でチームを牽引。スタメン11試合で平均11.5得点、3.9アシストを記録し、特に若いガード陣の経験不足を補うためゲームメイク役も担い、得点源の#14金丸晃輔、#54ダバンテ・ガードナーにも効率良くボールが配球されるようになった。
地区2位でも残留は危うい?混沌とする中地区
ただ先述したように、中地区2位の三河でも現時点では勝率が5割を下回っている状況だ。上昇の気配はあるものの、同地区2位以降の差は大きくなく、チャンピオンシップ出場圏内から一気に残留争いをしてしまう可能性もある。
昨季の地区王者・新潟アルビレックスはガードナーを失った代償が大きく、平均得点が昨季の80.2から70.8と大きくダウン。その原因は決定力で、3P%、FG%、FT%全てで数字を下げている。#30今村佳太の奮闘が光るものの、ガードナーとともにチームを支えていたベテラン陣の成績低下が顕著で、国内で実績豊富な#0エグゼビア・ギブソン頼みという厳しい状況にある。
それは富山グラウジーズも同様で、#34ジョシュア・スミスが今季絶望のケガをしたほか、#7阿部友和、#11宇都直輝ら主軸の離脱も痛手に。新潟の今村と同じく、若きスコアラー#12前田悟が新人王候補に挙げられる活躍を見せているが、チームを好転できるほどの影響力はまだない。
数字的には攻撃回数を測るPaceが昨季の76.8から74.7に低下。攻撃回数が減ったことで、得点と失点ともに減少しているが、ディフェンスが決して得意ではないためオフェンスの改善を図りたいところ。こちらもアイザック・バッツを獲得し、スミス以外のケガ人も復帰。復調の準備は整いつつある。
2位三河と3位富山とのゲーム差は2、4位の新潟とのゲーム差は4とまだまだ混戦模様だ。
今季に限っては下位の横浜と三遠にもチャンスあり
こうして2位以下が混戦なだけに、例年はチャンスがない地区下位のクラブも諦めるにはまだ早い状況だ。中地区5位の横浜ビー・コルセアーズはシーズン当初、課題のディフェンスを改善し、“今季こそ”の空気が漂っていたが、外国籍選手の入れ替えでチーム作りは振り出しに。12月以降は3勝13敗で地区2位から一気に残留争いのラインまで下降してしまった。
ディフェンスの崩壊という例年通りの悪い状況に戻ってしまい、失点の減少が急務だ。ただ#0ジェームズ・サザランド、#7レジナルド・ベクトンを軸にオフェンスが復調気味なのは唯一の救い。これに日本人選手が続くことで、相乗効果が期待できる。
一方、リーグ記録の開幕16連敗でここまで僅か3勝の三遠ネオフェニックス。外国籍選手を総入れ替えするなど、テコ入れを図っている中、超高校級プレーヤーの#0河村勇輝が加入し話題になった。今春から東海大学に進学するため、約1か月間の在籍となるが、デビュー戦となった1月25日と26日の千葉ジェッツ戦で、平均14.5得点、2.5アシストと素晴らしいパフォーマンスを見せた。
非常にクレバーな選手なだけに、よりチームバスケットを理解できれば存在感が増していくことは間違いない。18歳の双肩にチームの復調を委ねるのは少々酷ではあるが、起爆剤になることは間違いない。開幕時に比べればチームの状態は決して悪くなく、何かのきっかけをつかめば同地区2位まで駆け上がる可能性は十分ある。