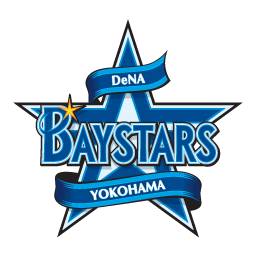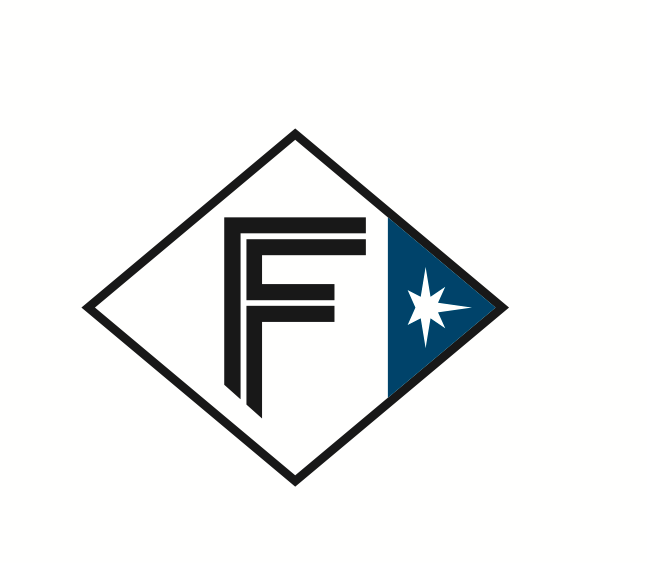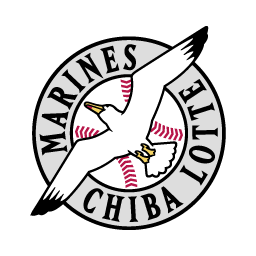プチ家出も
北京五輪が終わって、すぐに前を向けたわけではなかった。
北京後の1カ月半は全く練習をしなかった。それまでできなかったネイルアートをしてみたり、家族旅行にも行ったり。重量挙げだけだった頭を1回リセットすると、再びやる気が起こってきた。
ただ、親子の関係がうまくいかないこともあった。宏実が競技を始めてからというもの、父義行は練習時間を確保するために車で送り迎えをした。四六時中一緒に過ごすため、家では競技の話を避けたが、「親子だからこそ、突き詰めてしまいすぎる」ということは度々起きた。
お互いが言いたいことを言い過ぎ、けんかになることもあり、北京五輪翌年の2009年には宏実が家を飛び出し、沖縄の知人のもとで1週間練習するということもあった。ロンドン五輪前にも、助言を聞き入れずにけがをした娘に、父がバーベルをたたきつけて怒ったこともあった。
脱受け身
父娘がぶつかることばかり書いたが、北京からロンドンまでの4年間のキーワードは、いい意味での「親子離れ」だったと思う。
いつも父親がそばにいて、指示を出す。それも父親は名選手、名指導者だから、的確な指示である。いつしか、娘は受け身になる。そんな中で宏実の精神力は、決して強いとは言えなかった。
「大舞台で弱い」。というレッテルも貼られたこともあった。自身も「私、チキンハートなんです」と漏らしたこともある。
だから、北京後は技術もさることながら、精神面での強化に取り組んだと言っていい。
北京五輪の2年後だったと思う。宏実はこう語っていた。
「変わりたい」
それまでは父のつくった練習メニューをこなしてきたが、自分で考えたり、意見したりすることが増えてきた。「待っているのも嫌なんで」。
父も思っていた。「自分でやる、という気持ちがないと上にはいけない」。
その分、親子の衝突は増えたかもしれないが、1人のアスリートとしてみた時に、その衝突は必要だったかもしれない。
もちろん、その自立が親子関係に傷をもたらしたことはない。
ロンドン五輪の前、「父は心強い存在」と26歳になった宏実は言っていた。
父義行も、娘を表彰台に立たせてやりたいと思う気持ちでいっぱいだった。
「あそこに立てば、今までの苦しかったことも一瞬で忘れるから」
レッテルをはぐ
心を磨いた4年間だった。だからだろう、ロンドン五輪直前に宏実の口からこういう言葉が出ていた。
「今までの五輪は受け身だったけど、今度は攻めていく」
言葉通りの試技でもあった。それまで日本記録を持っていないほど苦手だった前半に行われるスナッチの1回目で、日本記録タイとなる83キロを成功した。この時点で精神的余裕が生まれたのだろう。過去2度の五輪とは違う笑みがロンドンでこぼれた。そして、競技を始めて12年、ついに三宅家3人目のメダリストになった。
それから4年。30歳になった宏実は2016年リオデジャネイロ五輪で、ケガで万全の状態ではない中で、2大会連続メダルとなる銅メダルを獲得した。
「大舞台で弱い」というレッテルはもうどこにもなかった。
本当は引退するつもりだった北京五輪から9年がたった。宏実は今年で32歳。肉体的なピークは過ぎたかもしれない。それでも3年後の東京五輪を目指す。(続く)
二つの東京五輪 日本人金メダル1号の重圧を背負う三宅家<5>