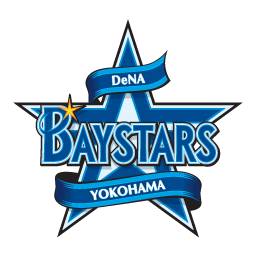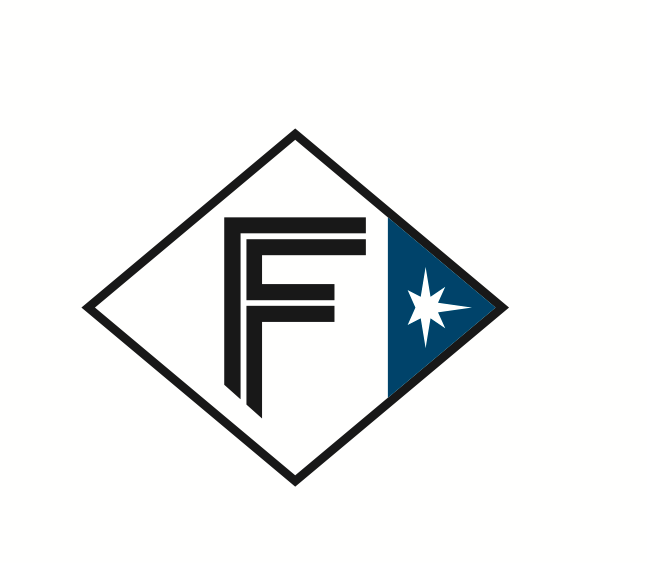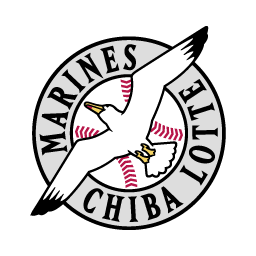アシスタントコーチとして日本代表にも帯同
-今年も結構タフな日程ですね?
恩塚監督:日本代表関連で昨年はアメリカに行っていましたので、昨年の方がきびしいかもしれないですね。今年の方が海外遠征は少ないですね。
-アシスタントコーチとして関わっている日本代表をどのようにご覧になっていますか?
恩塚監督:ベテラン選手のリーダーシップ、チームに貢献するとか、言葉に出来る態度はチームにすごく良い影響を与えていて、良いケミストリーに繋がっているのかなと思います。
-渡嘉敷来夢(JX-ENEOS)選手の日本代表復帰はかなり大きいですか?
恩塚監督:そうですね。コート上でバスケットボールプレイヤーとしてだけではなくて、コミュニケーションにおいて、コーチとプレイヤー、プレイヤー同士と、積極的にポジティブな言葉をかけ、良い影響を与えてくれていると思いますので。
-代表活動も楽しそうにされていますね。
恩塚監督:楽しいですね。大学とは違う楽しみですね。学べる機会が多いなあと。
良い選手は、技術だけでなくて考え方とか姿勢とか素晴らしいですね。そういうのに感動したり、そういうのが嬉しそうであり、楽しそうに見えます。

提供:東京医療保健大学女子バスケットボール部
ただ、ホーバスHCが怒り始めると、自分としてはバランス良くしていかないといけない――HCが色々話す時は若手が固まってしまうので、ほぐしてあげる必要があるなと。そのために笑顔で接するように心がけています。
練習の前や試合のハーフタイムで映像を使用
-試合のハーフタイム時にパソコンを使って指示をされていますが、どのような内容ですか?
恩塚監督:数字と映像を出しています。数字に関しては、得点・リバウンド・ターンオーバー、いわゆるスタッツです。映像は、前半の模様を録画しているのでそれを使用しています。
-どのようなことに気を付けて指示をされていますか?
恩塚監督:例えば、前半から後半に向けて「一番重要な修正点とかポイントは何か?」という事をハーフタイムに考えなければいけない――何を基準にして考えるか。その時にまず数字を見て、例えば前半点が伸びなかったとします。
・シュートが入らないからなのか?
・ターンオーバーが多いからなのか?
・オフェンスリバウンドが少ないからなのか?
これらはスタッツ上でわかりますよね。その上で、さらに実際自分が見ている部分をミックスしていて「ここがポイントだな」と思いながらビデオをピックアップしていくと、理解しやすいです。数字と自分の感覚でフィルターを持ちながら、そこの修正すべきポイントをプレイヤーにもレビューします。

Ⓒマンティー・チダ
-修正点をボードで書くよりも説得力が上がってくると?
恩塚監督:そうですね。自分はやっているつもりだけど、やっていなかった。オフェンスリバウンドに行っているつもりだけど、行っていなかった。ベストなパフォーマンスでリバウンドに行けていなかったということもわかるでしょう。
ターンオーバーが起こった時には、パスをする選手はパスを出したくてレシーバーが受けられる位置に立っていると考えていても、レシーバー側はパスコースを作ってあげられなかった、というのも確認できますよね。
-そういうことを明確に提示して良い方向に向かわせると?
恩塚監督:それがコーチの力ですよね。それができなかったらコーチが居る意味がないとも思っていて、だからこそしっかりアドバイスできるようにしたいなと思います。
恩塚監督のバスケ哲学
-恩塚監督のバスケに対する考え方はオフェンス重視、ディフェンス重視ですか?
恩塚監督:どちらも大事ですが、相手によります。どうやって勝てるかを考えて、その時にできるベストな選択をするというのが一番大きなミッションで、どの項目も大事だと考えています。その上で、このゲームにおいては、どの項目なのだろうかと優先順位を考えた方が、勝つ確率が上がりますよね。
「これが自分たちのスタイルだ」と言い続けても、それが相手にとって効果的で無ければ意味がないと思います。
-敢えて‟自分たちはこうだ”ということは示していないということでしょうか?
恩塚監督:そうですね。今年、良くチームに「バスケットボールをきちんとする。バスケットボールで勝つ。バスケットボールってどんなスポーツなのですか?」と話しをしています。
例えば、走る事とか、リバウンドに行くとか、ディフェンスでボールマンに絶えずプレッシャーをかけるとか、オフェンスで言えばアドバンテージを取った局面で1対1を仕掛けるとか、対応はどの相手でも変わらないわけです。そういうのをひと括りにして、バスケットボールをちゃんとするということなのですけど、それを持ちつつ重要なポイントは何なのか考えることですね。
-それができているか否かを見た上で、相手によって選手起用を変えてくるのですか?
恩塚監督:まあ、そこまで選手起用に影響はしないです。ただ、この相手であればこの選手、普段グレーな選手ではあるけれど行けるかな、と考えたりもします。
-すごく戦術の引き出しが多いですね。
恩塚監督:準備は大変ですよね。考えないといけないですから。試合する時に、色んなシチュエーションを全部想定します。
大事なのは、バスケットボールで考えたら適応能力だと思うんですよ。プレイヤーにもコーチにも適用して、その瞬間、‟行き詰っているところは何なのか”、‟強みは何なのか”、‟弱みは何なのか”、というのをちゃんと理解してプレーできるかどうかです。
-選手も頭を使いますね?
恩塚監督:使いますね。だから、できていない時は「ちゃんと見ろ」という合図を意味するジェスチャーを送ります。

Ⓒマンティー・チダ
-このような考えに至ったのは、コーチになってからですか?
恩塚監督:そうですね。結局、勝つという使命を頂いた時に、‟1%でも勝つ確率が上がる最善の方法は何だろうか”と考えるから、そこが理にかなっていないと、勝率は下がりますよね。でも、特殊なことはしないです。昔の方が、相手が面食らうことをしないと勝てないと思っていましたけど、結局世界でもナショナルチームでも、オリンピックとか、ワールドカップでも、魔法は無いです。ちゃんと自分たちがやろうとしていることを理解して、そのゲームの中で適応して正しく遂行する。それをよりエネルギッシュに最初から最後まで出し切れるかという勝負だと思っています。
-単純なようですが、いざアウトプットとなると大変ですね?
恩塚監督:勝負が決まる瞬間、あと一歩走れたら良かったとか、ちゃんと手を出していれば良かったとか、攻めの姿勢でチャンスをうかがっている選手が5人いるかいないかというところだと思います。解決策がわからなくて、ゲームへのプレッシャーがある中、対応するなんて無理ではないですか。解決できる確率は低くなりますよね。解決策は練習できちんと持っておくべきだなと思います。
-練習はその部分を重点的に行っていますか?
恩塚監督:もちろん。だからフリーの練習はしませんね。フリーの練習をしてもしょうがないと思っています。シチュエーション練習が多いです。自分でやりたい事が、思い通りにできる。対してディフェンスは「この考え方が効くよね」と。それが正確により高い強度でできるかというパフォーマンスだと思うので。
>>「東京医療保健大学女子バスケットボール部・インタビュー②恩塚亨監督」に続く