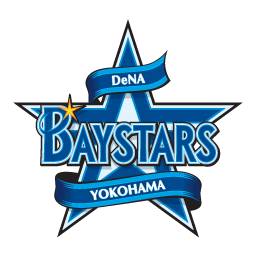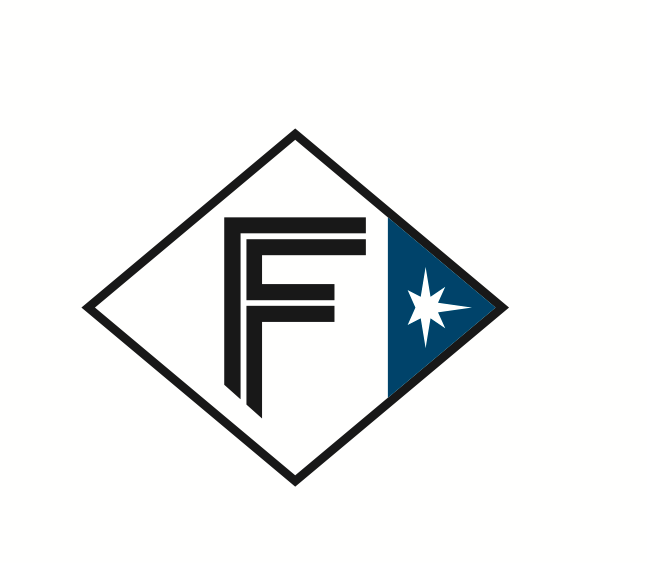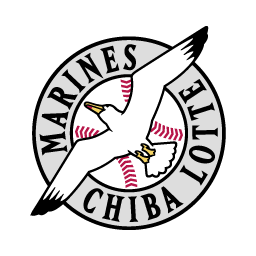日本ラグビーのプロ化構想
地元開催のラグビーワールドカップが閉幕し、日本ラグビー協会は、以前から公言していた日本ラグビーのプロ化に向けて、いよいよ具体的に動き出す。2021年秋に新リーグを発足させることを目指しており、今後スピード感を持って議論や決定が行われていくだろう。
日本ラグビー協会の清宮克幸副会長は、欧州ラグビーに匹敵する環太平洋リーグを設立し、年間収益は500億円を目指すという。
ラグビーW杯会場となった12都市を本拠地としたプロリーグを計画している。12都市は、札幌市、釜石市、熊谷市、調布市、横浜市、袋井市、豊田市、東大阪市、神戸市、福岡市、大分市、熊本市で、全国にまたがっている。近くにトップリーグのチームのある所もあるが、札幌のように強豪チームが存在しない場所もある。
清宮副会長は、トップリーグ内に、プロチームの所有を希望するチームが4~6あると言い、まずは8チームくらいでトップリーグの上位リーグとなる新リーグを発足させたい考えだ。
相思相愛の大学ラグビーと企業
プロ化に向けた動きを考えるためには、まず日本のラグビーが置かれた現状を見ていく必要がある。すると世界のラグビー先進地域とは、大きく異なることが見えてくる。
海外のラグビーは主に地域で発展したが、日本のラグビーは、教育機関と企業により発展してきた。高校、大学、会社の枠組みの中でプレーされており、伝統的に大学ラグビーの人気が高く、早慶戦や早明戦など大学同士の対抗意識で多くの学生やOBを観客席に動員している。
企業は社内の士気高揚や福利厚生としてラグビーを推進してきた経緯があり、収益を目的とした事業と考えておらず、集客や収入にそれほど力を入れてこなかったチームもある。チームによって、ラグビーの位置づけがまちまちで、実質ほぼプロチームのところもあれば、アマチュアの社会人ラグビーを貫いているチームもある。
実力では、社会人のほうが勝っているが、育成世代である大学ラグビーの方が人気があるというのは、世界でもあまり例がない。大学では現在アメリカの大学スポーツを統括するNCAAの日本版をつくる試みが行われている。これがどのように発展するかも注目だ。
日本の大学と企業は、非常に密接な関係にあり、企業チームの関係者が、大学で指導していることもよくある。また、体育会系の代表格であるラグビー部員は、集団行動に慣れており、忍耐力があることを期待されて、新卒採用でも人気がある。
プロ・アマ混在のメリットはセカンドキャリアと企業本体との関係強化
トップリーグは、現状全員がプロ選手ではなく社員としてプレーしている選手もいる。学生も進んで社員になる選手も少なくない。ラグビーは、肉体的消耗の激しいスポーツで、選手寿命は決して長くない。選手を引退した時に、企業が仕事をくれるという、セカンドキャリアまで考えてのことだ。
あえて社員選手とプロ選手を混在させているチームもある。このメリットは、実力派のプロ選手で強化する一方、社員という企業とのつながりの強いメンバーを置くことで、予算を用意してくれる会社本体との関係を強固にできることだ。
企業から分離し、プロリーグになったら、選手には競技で食べていくという覚悟が生まれる。一方で、企業から切り離された選手が引退した時、どのようなセカンドキャリアを提供できるかということも考える必要があるだろう。ラグビーは激しいコンタクトスポーツであり、怪我で引退を余儀なくされる選手も少なくない。育成世代を含め有望な選手が、将来への不安からプロリーグ参加に二の足を踏んでしまえば、リーグの発展を妨げることになってしまう。
プロ化は反対多数も2部化には成功
日本ラグビーのプロ化は以前、幾度となく議論されたが、企業チームの多くが反対し、実現できなかった。2003年にトップリーグが発足したが、社会人リーグという枠を外すことは出来なかった。
その後、浮き彫りになったのが、トップリーグと地域リーグの大きなギャップだ。降格したチームが翌シーズン、地域リーグで全勝し、トップリーグに復帰すると中々勝てないという状況もあった。
そこで新たに2017年に、8チームで始まったのが、2部に相当するトップチャレンジリーグだ。これにより、トップリーグ昇格前に実力が拮抗するチーム同士が年間を通じて対戦できるようになったことで、トップリーグの底上げにもつながった。あまり目立たないが、トップリーグを下から強化するこのリーグの存在は、日本ラグビーにとって大きい。
トップチャレンジリーグが出来たことで生まれるもう一つの効果、それは階層構造をもつ複数の全国規模のリーグの運営ノウハウが培われたことだ。Jリーグが複数リーグになるまでには8年の時を要した。また、プロリーグを目指しつつも、まだ実力や体制が十分ではないチームが出てきた際の受け皿となり、成長するチャンスを与えることが出来る。
もう一つの全国リーグであるトップチャレンジリーグをつくっていたことは、結果としてプロリーグ創設のいい準備になった。