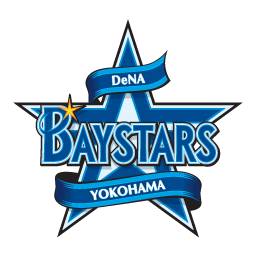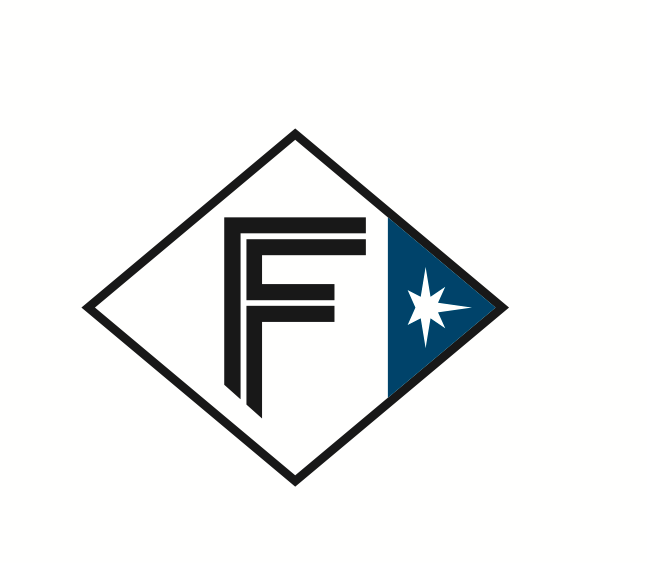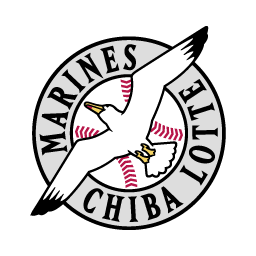9試合、2ヶ月ぶりの勝利
明治安田生命J1リーグ第31節、名古屋グランパスはホーム豊田スタジアムでヴィッセル神戸と対戦し3-0で勝利。8月10日の第22節川崎F戦以来9試合、およそ2ヶ月ぶり、そして風間八宏前監督からマッシモ・フィッカデンティ監督に交代して以来初めての勝利となった。
開幕3連勝。シーズン序盤は首位争いを繰り広げながらも、5月12日第12節から全く勝てなくなりおよそ3ヶ月間10試合勝利なし。第22節にようやく勝利を挙げたもののその後は再び勝てなくなり、ついにチームは残留争いに。さらには第26節終了後に風間八宏監督を解任と、苦しんだ期間が長かっただけに念願の勝利だった。
これでプレーオフ圏となる16位湘南との勝点差は5、自動降格圏となる17位松本との勝点差が6。もちろんまだ油断はできないが、J1残留には大きく近づいたのではないだろうか。
振り幅の大きい監督交代
3シーズン目を迎えた風間監督だが、昨季後半戦から今季序盤は迫力ある攻撃サッカーを展開していたものの、第26節を終え15試合でわずか1勝しか挙げられていないことを考えると解任は妥当とも言える。
ただ、後任がフィッカデンティ監督となったことで少し疑問を感じた方も多かったのではないだろうか。フィッカデンティ監督といえば過去率いたFC東京でも鳥栖でも堅守速攻スタイルで戦ってきた監督である。攻撃偏重ともいえる風間前監督とはあまりにもスタイルが違いすぎる。
風間スタイルにはファンも多かった。そして風間スタイルで一時的ではあるが昨季終盤から今季序盤は勝ち星を重ねていた。これまで全く結果が出なかったわけではない。そんな中、全く異なるスタイルの監督を招聘するということは、風間監督と積み上げてきた2年半は捨ててしまうことになる。
就任後の4試合で2分2敗と結果が出なかったことだけでなく、実際にフィッカデンティ監督が指揮をとってからはチームの戦い方が一気に堅守速攻へと変化したことで、監督交代という選択自体に疑問を持つ声も出始めていた。
融合が見えた新生名古屋の「テクニカルカウンター」
神戸戦での名古屋のボール支配率はわずか38%。パス数は名古屋の401本に対して神戸は625。アタッキングサードプレー数は名古屋の155に対して神戸は488。スタッツからみてもボールを保持する神戸と堅守速攻を狙う名古屋という構図に見えてしまう。
しかし実際にこの試合で名古屋が見せたのは、単純な堅守速攻スタイルではなかった。勝利の直接的な原因は前田直輝のスーパーゴールと切れ味鋭いドリブルでマッチアップしたジョアン・オマリを上回ったとも言えるが、そこに至るまでの部分に大きな特徴が見えた。
堅守速攻スタイルはその名のごとく堅い守りで好機を待ち素早く相手ゴール前までボールを運ぶことがポイントとなる。ということは縦パスの比率が増える。そして縦パスの比率が増えるということは、他の方向に比べて相手チームに拾われる可能性が高くパスの成功率も当然下がる。
ポゼッションサッカーであればパス成功率が80%を超えてくることが一般的だが、堅守速攻スタイルの場合はパス成功率が70%台となるのが通常。実際に同じ31節での残留争い直接対決、堅守速攻スタイル同士がぶつかりあった鳥栖対松本のパス成功率は鳥栖が73.5%、松本は74.7%である。
しかしこの試合での名古屋のパス成功率は80.8%。敵陣でのパス成功率も80.3%とまるでポゼッションサッカーのような、堅守速攻スタイルとしては非常に高い数字を記録した。
この数字からわかるのは名古屋は堅守速攻スタイルでありながら簡単にはボールを失わないということ。つまりポゼッションサッカーに比べれば回数は少ないが、カウンターでありながら敵陣まで確実にボールを運ぶことができているのだ。
もちろんこの結果には神戸の前線での守備の影響もあるだろうが、これは風間前監督と積み上げてきた2年半の攻撃的なパスサッカーで得た財産。風間前監督のテクニカルなパスサッカーとフィッカデンティ監督の堅守速攻スタイルが融合されたいわば「テクニカルカウンター」ができつつあるといえるだろう。
残り3試合は、鳥栖、磐田と残留を争うチームとの直接対決があり、最終節には優勝争いを繰り広げる鹿島との対戦と難しいカードが続くが、その3試合でも「テクニカルカウンター」を披露することができれば、J1残留に大きく近づくことになるだろう。