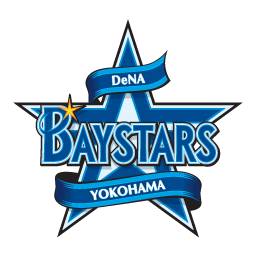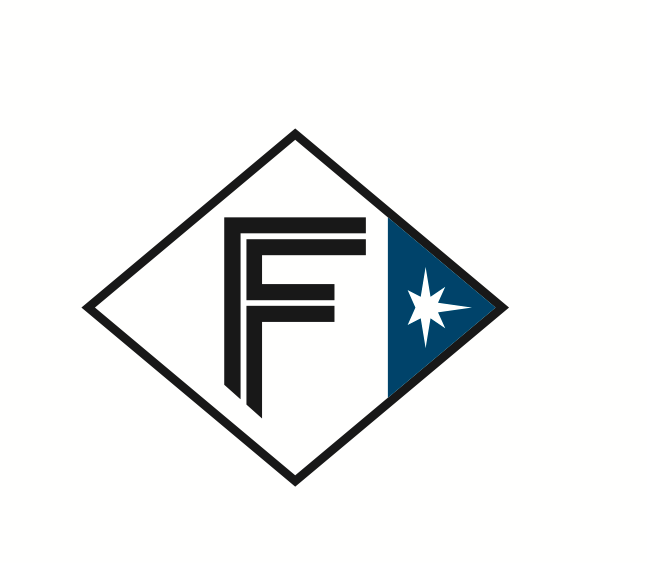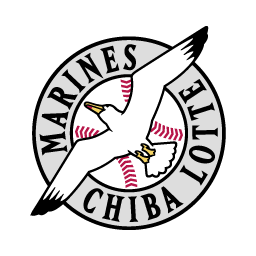4-4-2で自信を取り戻した仙台
開幕戦こそ引き分けたものの、そこから連敗したことで一時は最下位にまで順位を落としていたベガルタ仙台が少しずつ順位を上げている。
きっかけとなったのはフォーメーションの変更。第8節を終え1勝1分6敗と苦しんでいたが、直後のルヴァンカップ鳥栖戦でスタートのフォーメーションをこれまでの3バックから4-4-2へと変更。
リーグ戦でも第9節のガンバ大阪戦から4-4-2を採用すると、以降は6勝1分5敗と勝ち点を重ねることに成功し、第20節終了時点では13位。第18節、第19節では浦和、鹿島に連敗を喫したが、第20節では難敵C大阪に対して引き分け。もちろんピンチもあったが、内容的にも自信を取り戻すことができる試合だったのではないだろうか。
時計の針を戻したのではなく進めた
渡邉晋体制で6年目を迎えている仙台だが、元々は4-4-2のチームだった。2013年まで率いた手倉森監督(元長崎監督)はもちろん、2014年グラハム・アーノルド前監督が成績不振で退任し渡邉監督が引き継いでからも4-4-2。仙台といえば攻守の切り替えを重要視した堅守速攻スタイルの4-4-2だった。そこから3バックになったのが渡邉体制4年目の2017年。今では横浜FMやC大阪など取り入れるチームも増えてきたポジショナルプレーの概念をいち早く取り入れたことがきっかけだった。
そして再び布陣が4-4-2となったのだが、重要なのはポジショナルプレーの概念は継続していることだろう。
以前の堅守速攻スタイルに戻したのではなく、この2年間で培ったポジショナルプレーの概念を進化させた結果、たまたま同じ布陣になったに過ぎない。時計の針を戻したのではなく、進めたのである。
新しい4-4-2
今季の4-4-2が以前のものと異なることは実際の試合をみると直ぐにわかる。布陣は4-4-2というもののボール保持では両SBが前に出て両SHは中に入る。2人のCBと2人の守備的MFが後方に残る2-2-4-2の様なポジショニングを行っている。
そしてこのポジショニングでは、同じ高さにいる選手はピッチを縦に5分割したレーンの同じレーンには入らない。つまり選手間の距離を近づけない。
これは「5レーン理論」と呼ばれているもので、自分たちのポジショニングによって相手の守備陣形を動かそうとするポジショナルプレーの原則的な考え方。それが確実にチームに根付いた上での4-4-2になっているのだ。
その結果前節のC大阪戦では、どちらも布陣は4-4-2であることから一般的にはマッチアップする相手がハッキリとする「ミラーゲーム」となることが多いのだが、どちらもポジショナルプレーの原則を持つチーム。如何にして相手の陣形を動かすかという見どころの多い試合だった。
一番のメリットは守備の安定
この布陣変更で大きな効果をあげているのは守備の安定だろう。
3バックだった第8節までの8試合で複数失点を喫した試合が5試合だったのに対し、4バックとなった第9節から第20節までの12試合での複数失点は4試合。簡単に失点を重ねる試合が少なくなった。
守備が改善されつつある要因としては2つ考えられる。
1つは自陣ゴール前でコンパクトな守備陣形を作ることができるようになったこと。4バックの4人がペナルティエリアの幅を厳守することで、自陣ゴール前でむやみにスペースを開けてしまうことがなくなった。
そして2つめは今季加入のシマオ・マテがハマるポジションを見つけ出したことだ。
3バックの時のシマオ・マテは主に守備的MFのポジションで起用されていた。2013年から2016年までスペイン1部のレバンテで活躍していた実績を持つシマオ・マテは強さと速さと高さを兼ね備え、特に前への強さは特筆すべきものがある選手である。しかし今季序盤は前へと出た後のスペースを使われることが多く、強みが裏目に出る形となっていたが、4バックとなりCBへと移ってからは改善。選手間の距離が常に適切に保たれることで前へ出た後のカバーも容易になり、本人も思い切って自分の強みを出せるようになったのだ。
一時は最下位にまで落ちてしまったが持ち直してきた仙台。失点数はまだまだ多いのでさらなる改善は求められるが、ここから楽しみなチームの1つだ。