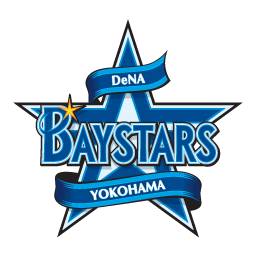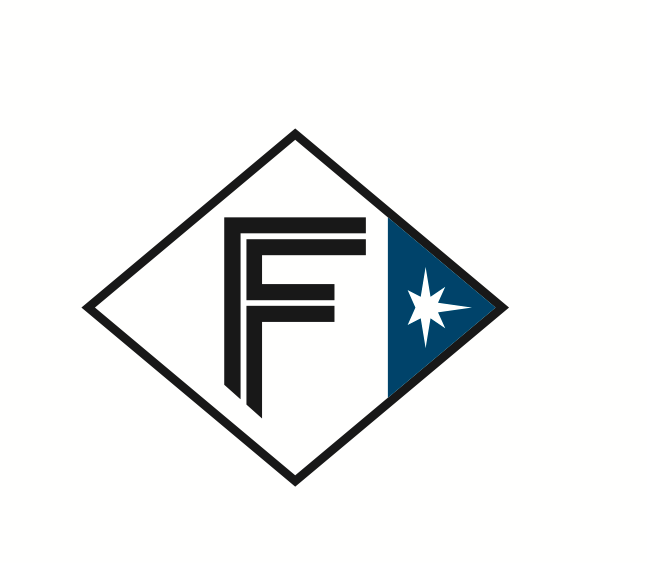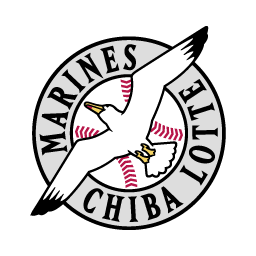ラモス監督率いる日本代表が戦うビーチサッカーW杯
11月21日からワールドカップが行われていることをご存知だろうか?開催されているのはFIFA ビーチサッカー ワールドカップ パラグアイ 2019。パラグアイでラモス瑠偉監督率いる日本代表が快進撃を見せている。
ビーチサッカー。競技自体の名前を聞いたことがある方は多いだろう。ちょっとしたハイライト映像を見たことがあるという方もいるだろう。
しかし実際の試合を1試合通して見たことあるという方は少ないのではないだろうか。そんな方に是非見ていただきたいのがビーチサッカー ワールドカップ。日本代表の快進撃はもちろんだが、アクロバティックなプレーが続くビーチサッカー自体が面白いのだ。
ビーチサッカーのルールを紹介
ビーチサッカーは12分×3ピリオドで行われ、1チーム5人で試合中の交代は自由。ピッチのサイズはフットサルとほぼ同じだがより正方形に近くなっており、ゴールはフットサルのものよりも横幅が広い。ちょうど小学生用のゴールとほぼ同じサイズとなっている。
フットサルとルーツが同じなのでポジション名もフットサルと同じ。サッカーでいうGKがゴレイロ、DFがフィクソ、MFがアラ、FWがピヴォと呼ばれる。
最大の特徴はピッチが砂であるということ。そのためピッチはデコボコ。グラウンダーのボールはイレギュラーバウンドが起こるので、ほとんどのプレーが浮き球で行われる。ショルダーチャージなどの接触プレーは原則ファールとなるため、シュートは普通のサッカーではあまりお目にかからないオーバーヘッドシュート(バイシクルシュート)が大きな武器となる。
少し戦術的な部分にも触れるとゴレイロ(GK)の使い方が大きなポイント。攻撃側はゴレイロで必ず数的優位を作ることができる。先ほどは基本的に浮き球で行うと説明したが、敢えてイレギュラーバウンドを狙ったテクニカルなロングシュートで得点を決めることもできる。
そのため守備側は攻撃側のゴレイロに対してどの様に対応するか。闇雲に突撃すればただただピンチを招くためチーム全体の連動が重要。そして攻撃側は相手がゴレイロにアプローチをかけてきた時にピッチのどこかで必ず生まれるフリーの選手をうまく使うことができれば一気に得点のチャンスとなる。
ワールドカップで快進撃を見せる日本代表
FIFA ビーチサッカー ワールドカップ パラグアイ 2019。開催国パラグアイと同じグループAに入った日本はグループリーグ3試合を3連勝。1位でグループを突破し、決勝トーナメント1回戦となる準々決勝ウルグアイ戦も3-2で勝利。2005年第1回大会以来となる2度目のベスト4進出を決めた。これまでの最高成績はこの第1回大会の4位。ここから日本は歴史を変える戦いに挑むことになる。
日本代表の中心選手は背番号10番のキャプテン茂怜羅オズ。「世界最高のフィクソ」と呼ばれ世界ベスト5プレイヤーに過去4度選出。190cm/90kgのフィジカルだけでなくテクニックも抜群。さらに得点力も兼ね備えているまさにワールドクラスの選手である。
ブラジル代表に選出される可能性も十分あったが、2007年に日本に渡ったことが大きな転機となり、2012年に日本国籍を取得。ラモス監督同様「リオ生まれのサムライ」だ。
ピヴォとしてチームを牽引しているのは2番の赤熊卓弥。得点力のある後藤崇介が直前の合宿での怪我のため代表から外れることとなった際は不安視されたが、大会直前までの不調から完全に脱却した赤熊が前線で身体をはり、ゴールを量産。開幕戦となるパラグアイ戦では残り0.5秒で決勝ゴールを決め、チームに勢いをもたらした。
ボールを恐れず顔面ブロックで好セーブを見せるゴレイロ照喜名辰吾、開幕戦でゴールマウスを守った宜野座寛也。40歳のベテラン田畑輝樹、チーム最年少の大場崇晃。トリッキーなプレーが得意な小牧正幸ら、魅力ある選手が揃うビーチサッカー日本代表が世界の頂点を目指す。
FIFA ビーチサッカー ワールドカップ パラグアイ 2019 ベスト4に進出した日本。歴史を変える戦いは日本時間12月1日の朝6時から準決勝。勝利すれば12月2日朝(現地時間12月1日)の決勝へと進出する。