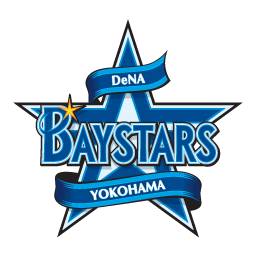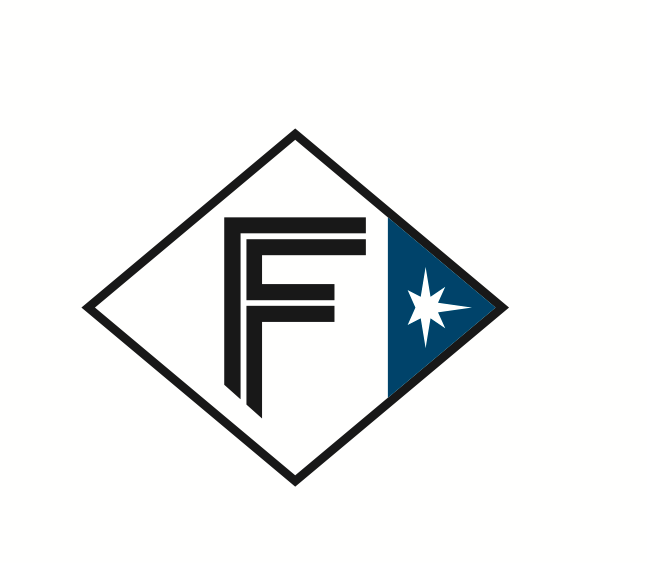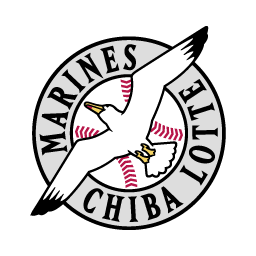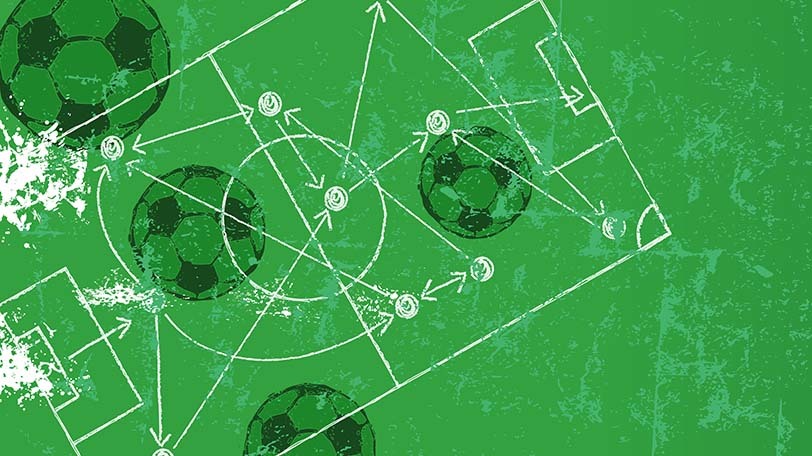コンセプトであり評価基準
Jリーグでも聞かれるようになった「ポジショナルプレー」。今ひとつよくわからないという人も多いのではないだろうか。
「ポジショナルプレー」という言葉自体がチェス用語ということもあり、チェスがあまり一般的では無い日本では理解しにくいという面もあるのだろう。
しかし「ポジショナルプレー」は現在そしてこれからのサッカーを考える上で重要なキーワードとなり得る言葉でもある。
Jリーグで「ポジショナルプレー」という言葉が聞かれるようになったことは、スペイン系の監督が増えてきたことと関係している。先日まで神戸の監督を務めていたスペイン人のファン・マヌエル・リージョが「ポジショナルプレー」の第一人者だからだ。
源流となるものは古くからあったのだが、それを1つの考え方にまとめ「ポジショナルプレー(ポジションプレー)」として名前をつけたのがリージョ。そして、それを広めたのが現マンチェスター・シティの監督であるグアルディオラだ。
「ポジショナルプレー」自体が一般的ではなかった2011年、「ポジショナルプレーとは何か?」という質問に対し、リージョが答えた「コンセプトであり評価基準だ」は、実に良くできた答えだった。
サッカーには「ポゼッション」や「カウンター」という戦術を表す言葉がいくつもあるが、これらは全て戦い方を表したもの。また、「ポジショナルプレー」と「ポゼッションサッカー」の語感が似ているため、混同されることや、「ポジショナルプレーはポゼッションサッカーの一種」と勘違いされることも多い。
しかし、「ポジショナルプレー」は戦い方ではなくコンセプト(概念)だ。つまり、もっと原則的な部分を指すため、「ポジショナルプレー」と「ポゼッションサッカー」は全く別の階層にあり、比較や同一視することはナンセンスなのだ。