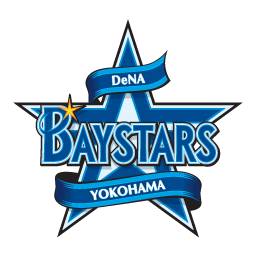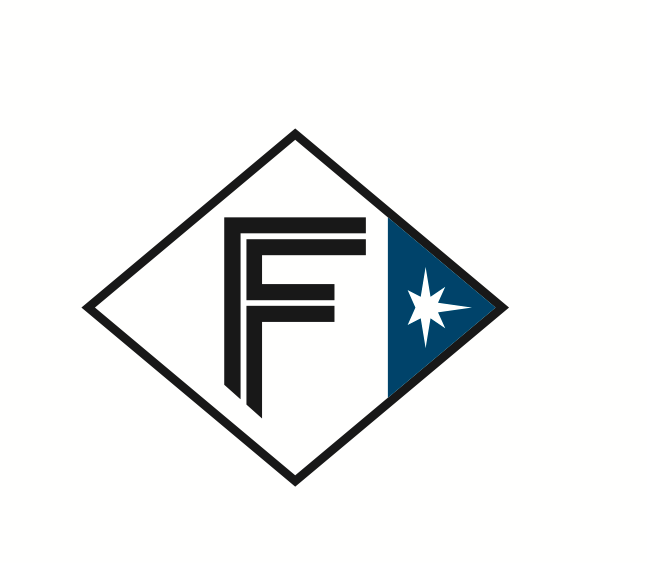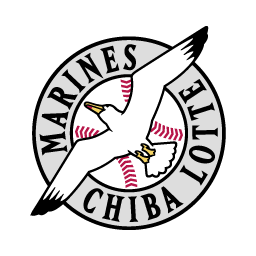最大5回の応募チャンス、自己PR文必要
来年3月26日から47都道府県を巡る五輪聖火リレーのルート概要が発表され、平和や希望を象徴するトーチをつなぐ聖火ランナーの募集も今月17日から順次始まることになった。公募するのは各都道府県とスポンサー企業4社。1人最大5回の応募チャンスがあるが、走れるのは1回だけだ。
聖火リレーは東日本大震災などの被災地、全国各地の世界遺産や名所を組み込み、通過する市区町村は日本全体のほぼ半分の857自治体、121日間で総勢約1万人のランナーがリレーする全国フェスティバル。各都道府県の実行委員会が選ぶのは約2500人で、このうち半数以上が公募となるが、一般枠は「狭き門」になりそうだ。

ⒸSPAIA
地元に縁がある人、最年少は中1
応募はまず、2008年4月1日以前に生まれた人が条件となる。大会を中学1年生として迎える子どもが最も若いランナーとなる可能性がある。来年3月1日時点で18歳未満の場合は保護者の同意が必要だ。性別や国籍は問われない。
一方、政治や宗教に絡むメッセージを発することが目的の人、議員・首長やその候補者、政党の党首などは対象外だ。
一般公募はスポンサーの日本コカ・コーラの17日を皮切りに、トヨタ自動車と日本生命保険、NTTの3社が24日、各都道府県実行委は7月1日から募集を順次開始する。いずれも募集期間は8月31日まで。
走りたい都道府県に住んだことがある、通勤・通学先があるなど、その土地に何らかの縁を持つことが前提となる。地域で活動している人を中心に選定される見通しで、その土地と無関係の人は基本的に認められない。
1人200メートル、ユニホーム無償支給
ランナーは自分の意思で安全に聖火を運べることは原則として必要だが、車いす利用のほか、補助犬、介助者のサポートを受けることも可能だ。日時や場所は選べず、聖火リレーのコンセプト「希望の道を、つなごう。」を象徴するように駅伝のたすきをモチーフにした赤と白のユニホームは無償支給されるが、交通費や宿泊費は自己負担となる。走った人で希望者はトーチを5万円程度で購入することもできる。
これらの条件を満たせば誰でも応募が可能。都道府県の一つと、スポンサー4社に各1回ずつ最大5回まで応募でき、自己PR文を提出する。ランナー決定の連絡は12月以降に届く予定だ。
走る距離は1人当たり約200メートル。1日に走れる人は都道府県枠が22人、スポンサー枠が60人程度で計80人前後となる見込み。スポンサー枠の公募が何割程度かは非公表で、国際オリンピック委員会(IOC)の推薦枠などもあるため、一般ランナーの倍率がどの程度になるかは不透明だ。ただ半世紀ぶりの自国の夏季五輪だけに高倍率が予想される。
大音量の音楽で先導
厳粛な雰囲気があった1964年の東京大会とは様変わりし、近年の聖火リレーはスポンサーのロゴが入った数台のトラックが大音量の音楽で先導し、イベント色が強い。ランナーはSNSで発信し、テレビカメラに向かってインタビューに応じたり、ポーズを取ったり、若者を意識したイベントに変化している。
五輪の歴史で聖火リレーが初めて登場したのは、国威発揚を狙ったヒトラーのナチス政権下で開かれた1936年ベルリン大会。古代五輪発祥の地、ギリシャ西部のオリンピアで採火した聖火を運ぶスタイルを考案した。
水中や宇宙遊泳も
60年ローマ大会では初めてテレビ中継。64年東京大会ではギリシャを出発後にトルコやレバノン、イランなどを巡ってから日本に到着した。従来は開催都市まで国際ルートが一般的だったが、世界最高峰のチョモランマ(英語名エベレスト)山頂にも登頂した2008年北京大会で、政治上の問題から妨害行為が各地で発生したことで廃止された。
最近は技術の進歩に伴い、2000年シドニー大会では、水の中でも燃え続けるトーチを使い「水中リレー」が実現。14年冬季ソチ大会では、宇宙飛行士がトーチとともに宇宙遊泳をして話題を呼んだ。18年平昌冬季五輪ではロボットを活用するなど、国を挙げて趣向を凝らすようになってきている。