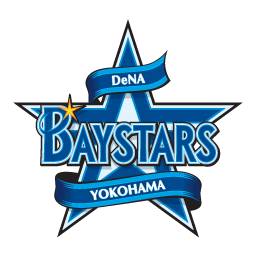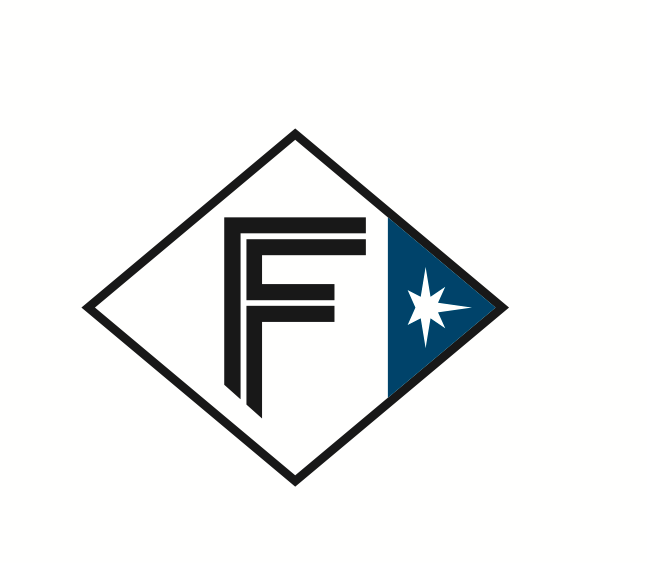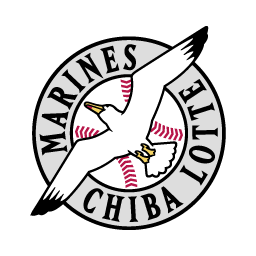打席と打数は何が違うのか?
打席と打数、どちらも同じような意味で使われるように感じるが、その内容は異なる。
打席とは、そのまま「打席に立った回数」のことを指している。1試合で4回バッターボックスに立つチャンスが巡ってきたとしたら、それは「4打席」となる。
一方で打数というのは「打席数-(四球+死球+犠打+犠飛+打撃妨害+走塁妨害)」という計算で求められる。四球や死球は投手側に責任があるため打数には数えられない。また犠打や犠飛は、自身の安打を犠牲にする戦略の一つであり、こちらも打数には含まれない。
つまり、バッターボックスに立った回数(打席数)から、自分ではどうしようもないプレー結果と、ヒットを捨てて自らを犠牲にしたと考えられるプレーの数を引いたものが打数であり、その数は打席数よりも少なくなることがほとんどだ。
同じような意味で使ってしまいそうな打席と打数だが、異なる意味の数字のことを表している。
打席を使う場面は
打席を使う場面といえば、真っ先に思い浮かぶのは「規定打席」。日本のプロ野球やアメリカのメジャーリーグでは打率や出塁率などの打撃ランキングが存在するが、これらは基本的に、規定打席以上の選手を対象にしている。計算式は次の通り。
規定打席=試合数×3.1
これは、この計算式が作られた頃のメジャーリーグで、打撃ランキングのタイトルの一つ「首位打者」を争う選手の打席数が、おおよそこの辺りに落ち着くことから採用され、その後日本にも導入されたという経緯がある。
ちなみに、打撃タイトルの首位打者、最高長打率、最高出塁率については、規定打席に到達していない場合でも、例外ルールによって首位打者や最高出塁率として評価されることもある。その内容は厳しく、例外ルールが定められた年(首位打者1967年、最高長打率1984年、最高出塁率2008年)以降に条件をクリアした選手は2019年終了時点では存在しない。
例外ルールの内容は、野球規則10・22(a)の但書に記されており、「ただし、必要な打席数に満たない打者でも、その不足数を打数として加算し、なお最高の打率、長打率、出塁率になった場合には、この打者がリーグの首位打者、最高長打率打者、最高出塁率打者となる」というものである。
これはどういうことかというと、規定打席に到達していなかった場合に、足りない打席数を、凡打を打ったものと仮定(凡打は安打ではなく、出塁もしないため打数のみがカウントされる)しても1位の選手の数字を上回れば首位打者、最高長打率、最高出塁率として認定するというものである。
打数を使う場面は
打席と比較して、活用される場面が多いのが打数。打数は、打率を求めるために使われることが多い。打率は「安打数÷打数」、長打率は「塁打数÷打数」、得点圏打率は「一塁以外に走者がいる場合の安打数÷一塁以外に走者がいる場合の打数」という計算で求めることができる。日本のプロ野球においても、アメリカのメジャーリーグにおいても、打率が3割を超える選手は好打者として高く評価される。
打数は他にも、出塁率([安打+四球+死球]÷[打数+四球+死球+犠飛])を求める際にも使われる。
「打席数-(四球+死球+犠打+犠飛+打撃妨害+走塁妨害)」という打数の中で、安打や塁打をどれだけ出せるのかというのは、選手それぞれの資質や調子を見極めるための、非常に重要なポイントと考えられているのだ。
打席と打数、なんとなく耳にしていても、その正確な意味を把握できている方は、野球ファン以外では意外と少ないのかもしれない。しかし打席と打数、それぞれが意味するところをしっかりと理解できていれば、何となく見ているテレビの野球解説や試合観戦もより面白くなるのではないだろうか。チームとしての勝利はもちろんのこと、ぜひ選手一人一人の活躍を表す数字にも目を向けてみて欲しい。