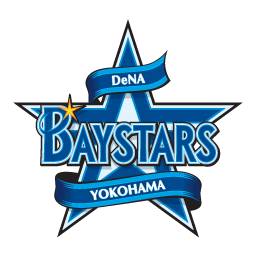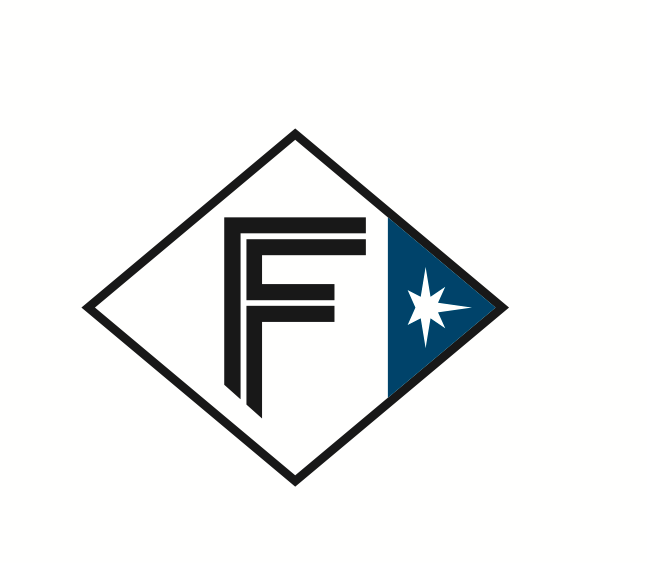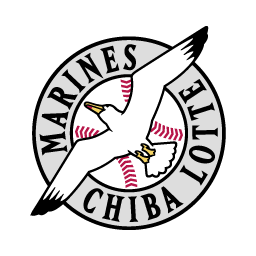優勝の権利を持つ2チームによる直接対決
J1最終節に組まれていたのは優勝の権利を持つ2チームによる直接対決。まさにビッグカードである。優位に立つのは横浜FM。勝点差が3あり、得失点差でも上回る。FC東京が逆転優勝するには4点差以上の勝利が必要となる。
FC東京にも全く可能性が無いわけではない。実際に第17節での対戦ではFC東京が4得点を奪い勝利している。アグレッシブに敵陣でサッカーをしようとする横浜FMの戦い方はその反面自陣には大きなスペースを作ることとなる。そのためFC東京が得意としているカウンターの餌食にもなりやすいからだ。
横浜FMは扇原、FC東京はディエゴ・オリヴェイラ、室屋という主力を欠く中での対戦となったが、両チーム共に十分な準備をしての最終決戦となった。
貫き通した横浜FM
最初にビッグチャンスを迎えたのはFC東京。23分に後ろから飛び出した永井がGKと1対1の場面を迎えている。しかしこの場面を横浜FMのGK朴一圭がセーブ。するとその直後の26分に横浜FMはティーラトンのミドルシュートで先制することに成功した。
この一連の流れは今季の横浜FMを象徴するようなシーンだった。
最初に作られた決定機だが、横浜FMは敵陣でアグレッシブにプレーしようとする。具体的に言えば選手のポジショニングを整理することで縦パスを入れるための選択肢を増やし、チャンスがあればそこに縦パスをいれる。もちろん縦パスは成功率が下がるので相手に奪われることもあるが、そうなれば攻守の切り替えのスピードを上げてすぐにボールを奪い返す。相手に息をつく暇も与えない「敵陣制圧スタイル」のサッカーである。
しかしその分どうしても自陣にスペースが生まれる。ボールを奪われた時のアプローチが遅れると一気にカウンターの危機を迎えることとなる。そのために準備をしているのが、CBティアゴ・マルティンスとGK朴一圭。ティアゴ・マルティンスは屈強なフィジカルと抜群のスピードで広範囲をカバー。また朴一圭も広い守備範囲と抜群の反応を見せる。永井の決定機を止めた場面はまさにそれだ。
そして得点を決めたティーラトン。左SBの選手でありながら中央からミドルシュートを決めてみせた。SBの選手が中央に入ってくるのも横浜FMの特徴。横浜FMのSBは攻守において中盤を制圧するためにサイドにいるだけではなく中央に入ってくるため、守備側はどうしても中央で数的不利を作られる。
この場面でもFC東京の東は数的不利を作られ2度追いを強いられていたために対応に遅れが出てしまった。結果、ティーラトンのシュートが東に当たりボールはゴールに吸い込まれた。
さらに44分にはエリキが追加点。62分には朴一圭が永井を倒し退場となるも、横浜FMは77分にさらに遠藤が追加点を奪い3-0。「大量失点さえしなければ優勝」というアドバンテージを持っての試合だったが、アドバンテージは関係なく真っ向勝負でスタイルを貫き通し優勝を掴んだ。
横浜FMの優勝はJリーグが変わるきっかけになるか
今季の横浜FMの優勝はこれからのJリーグにとって大きな分岐点となる可能性がある。それは横浜FMがマンチェスター・シティなどを傘下に持つシティ・フットボール・グループ(CFG)と提携し、チーム運営に強力なバックアップを受けているからだ。
Jリーグでは親会社の意向やOB、学閥などが運営に影響しているクラブが多い。そんなJリーグにあって、横浜FMは外国資本を本格的に受けいれた。CFGの世界中に張り巡らされたネットワークと世界レベルのフットボールのプロ集団の支援を受け、5年をかけてそのノウハウを取り入れてきた。
例えスター選手であったとしてもチームの進むべき方向にいない選手が整理されることもある。一方で、進む方向に合致していれば1年目で苦しんだポステコグルー監督にそうしたようにクラブとして支え、世界的なネットワークを使ってチームの方向性に適した選手を獲得する。
そうやって今季の戦術的に高いレベルで整備されたチームが作り上げられ、見事に優勝という結果を掴み取った。様々な業界でグローバル化という言葉が当たり前になり久しいが、Jリーグにもいよいよグローバル化、世界基準の波が押し寄せてくるのではないだろうか。